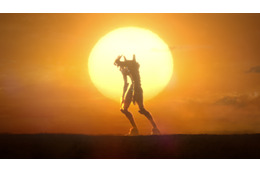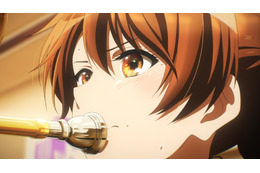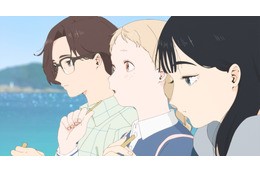――第20回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の審査委員である高橋良輔さんは、講評で「むずかしい題材へのチャレンジ」、そしてマンガをアニメに落とし込む際に加えられた「動き」と「音」の魅力について激賞されています。それぞれについてうかがわせてください。まずイジメや障害、自殺衝動といったシリアスなモチーフが扱われていますが、それらを描くうえで注意された点はどこですか?
山田
シリアスな面が注目されやすい作品ではありますけど、私はこの作品はそれを見せるための作品ではないと思っているんですね。なのでそのことを観た人にわかってもらえるようにしなければいけないなと。そのために、作中で描かれるどの行為に関しても、否定するでも肯定するでもなく、それぞれの登場人物の心に寄り添うように描くことを大切にしました。
――「動き」に関しては、注目ポイントの一つに、細やかな「手話」の描写があると思います。アニメで描くにはむずかしいモチーフだと思いますが、どのような手順で制作されたのでしょうか。
山田
手話は繊細な言語なので、少しの違い、たとえば手のひらの向きが少し違うだけで意味が変わってしまうそうなんですね。なので最初に、できあがった絵コンテを手話監修の方に見ていただいて、そのうえで手話が登場するシーンすべてを実演していただきました。アニメーターの方には、その参考映像をもとにして、芝居を起こしてもらっています。ただその際も、動作として正確に描くだけでなく、手話を使っている人ごとの性格や修練度合いの違いも大事にしながら演技付けをしていきました。

――また「動き」に関してもう一点。山田監督はしばしば、人物の感情を表現する際の方法論として、“足”の動きや描写にこだわりを持つ映像作家として言及されてきました。今作ではいかがでしたか。
山田
足元を映すことは、いままでもこれといった決まりごとがあってやってきたわけではなくて、そのときどきで必要なものに寄り添っていった結果、自然と多くなっていたんだと思います。今回は将也の物語なので、カメラワークに関しても“将也が見ることのできる世界”を軸に考えていきました。“将也自身が選び取って見ているもの”と、“将也に気づきが訪れたときに見えてくるもの”、その二つの世界を積み上げて編み込んだつもりです。
――「音」に関しては、音楽家である牛尾憲輔さんとの密な共同制作による、ノイズを活かした独特の劇伴が大きな注目を集めました。どのような手順で制作されたのでしょうか。
山田
牛尾さんとの音作りは、最初の顔合わせのときに“作品づくりの概念”みたいな抽象的なお話をして、「いまのお話を受けてまず何か1曲書いてみます」というところからはじまりました。それから絵コンテが少し進むたびにお見せしては、それを読んだ牛尾さんから「スケッチです」と新しい音楽が届くということの繰り返しで、気が付けばあらためて楽曲を発注するまでもなく、作品世界に寄り添った音楽ができあがっていました。またその後も、完成画面に音を当てはめていくダビング作業まで、相談し合いながら一緒にやりましたね。

――映像と音響が相互に刺激し合い高め合う特殊な制作スタイルだと思いますが、なぜそこまで「音」にこだわられたのでしょうか?
山田
この作品は“人の生理に寄り添う”作品だと思ったからです。そこから胎内……というか体内、生きているものの体の内側に必ず存在する“音”というものを“見る”、もっと言うと“体験する”ような作品にしたいなと。
音は“聞こえ”のものとしてとらえられることが多いと思うんですけど、それだけではなくて、周波数によっては身体に振動を与えたりとか、あらゆるものに紐付いた現象だと思うんですね。それを一つのフィルムにまとめ上げていくことが、この作品にとって、とても意味のあることだと思ったので……ってすみません、うまくまとまらなくて……。
――とんでもないです。よくわかります。
山田
素直には……“音”を映画にしたかったんだと思います。
――まさに“音聲(おんせい)の形”を作り上げられたということだと思いますが、手応えはいかがでしたか?
山田
すごく刺激になりましたね。今回の経験を通じて、今後さらに挑戦してみたいことが見つかりました。
■次ページ:色やにおいを感じさせる作品世界を信じて