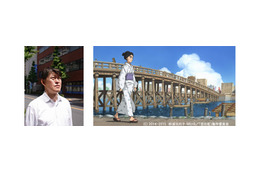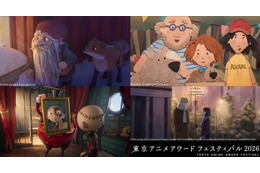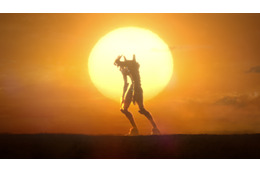この特集上映に先んじて、「アニメ!アニメ!」では原監督にフィルモグラフィーを振り返りながら話をうかがった。国内外の映画祭で数々の賞を受賞して高い評価を受ける原監督の、作品作りに向かう眼差しはいったいどのようなものなのか。原監督作品を鑑賞する際の一助となれば幸いである。また、今後の作品作りに関しても力強い言葉をいただいたので、ぜひ最後までお読みいただきたい。
[取材・構成=細川洋平]
第30回東京国際映画祭
■開催期間:2017年10月25日(水)~11月3日(金・祝)
■会場:六本木ヒルズ(港区)、EXシアター六本木 他
http://2017.tiff-jp.net/ja/

――第30回東京国際映画祭(TIFF2017)では原恵一監督の特集上映が行われます。この機会に原監督のフィルモグラフィーを振り返ったお話をうかがえればと思いますが、まずはじめに、演出のお仕事を意識しはじめたのはいつ頃なのでしょうか。
原恵一監督(以下、原)
業界に入った時から演出をやりたいと思っていましたけど、大きなきっかけは『ドラえもん のび太の魔界大冒険』(1984)に参加した時です。監督の芝山努さんによる絵コンテがものすごくおもしろかった。アニメーションでは絵コンテというものが非常に重要になるのですが、他のものと比べても芝山さんは群を抜いていて、絵コンテによる芝居の間や緩急を的確に心得ている人だったんです。その時に「あ、絵コンテってこんなにおもしろいんだ」と感じ、以来自分もずっと芝山さんみたいな絵コンテを描きたいと思いながらやって来ました。
――それでは、原監督がかねてから影響を受けた人として挙げていらっしゃる木下惠介監督を意識するようになるのはいつ頃のことなのでしょう。
原
シンエイ動画でドラえもんの演出をやっていた頃、ある名画座で木下監督の特集を見てからですね。ものすごくおもしろくて、あのおもしろさに自分も近づきたいという意識、それがどこかで芽生えたんです。絵コンテにも影響は出ていると思います。それがどこかは簡単には言えないですけれどもね。
――TIFF2017にラインナップされている『エスパー魔美 星空のダンシングドール』やTVシリーズ2作も顕著ですが、物語は魔美の超能力を駆使して物事を解決するのではなく、当事者たちが自らの力で解決していきます。こういった作品作りには当時の原監督の中の気分や時代の流れのようなものがあったのでしょうか。
原
特にそういうものを意識したわけではないですけど。何だろうな……『エスパー魔美』は佐倉魔美というとても明るくてピュアでかわいい女の子が、突然手に入れた超能力を何とか世の中のために使うということを描いた作品です。けれど、そのために魔美は今まで見ずに済んでいた人間の醜さや悪意にたくさん出会うことになり、悩んだり憤ったり喜んだりする。その中学2年生の女の子の心の動きを、キチンとしたドラマとして作りたいという気持ちが僕には強かったんですね。おそらく藤子・F・不二雄先生もそういった人間のドラマを描きたかったのではないかと思うんですよ。当時、20代でチーフディレクターを任されたのですが、藤子先生の描く『エスパー魔美』を誰よりもわかっているという自負があったので、なるべく自分にウソをつかずに作ろうと思っていました。そのため、派手な作品にしたいと考えていたプロデューサーやテレビ局の人たちとは放送初期によくぶつかっていましたね(笑)。

――作品作りを通して、監督のやりたいことが間違っていないと証明していったんですね。
原
そうです。
――『エスパー魔美』だけではなく『カラフル』以前の作品には、問題の当事者と他者、つまり問題を外側から見つめる視線が作品に織り込まれていて、この構図は原監督のこだわりにも見えます。
原
ええ。同じものを見ても人によって感じるものが違う、そういう複雑な見え方をなるべく意識したいなと思っていますね。そういうことをまさに藤子先生や木下監督の作品から僕は学んだと思っています。
――「分かりやすい作品」とは違う作品作りをすることで、例えば意図とは違った見方・受け取られ方をされてしまう可能性も出てくるかと思います。そういった歯がゆさといいますか、”伝わらない可能性”とはどう向き合われてきたのでしょうか。
原
映画にもアニメにも時代のトレンドはあると思うんですけれど、僕はそういうものにあんまり流されたくないんですね。もちろん僕は商業作品の監督なので、お客さんへのサービスも忘れたことはないつもりですけど、今、ハリウッド映画のトレンドは”誰もが分かるもの”ですよね。曖昧な部分はどんどん排除して、「アトラクション化」して行っているような気がするんです。
――ああ、そうですね。
原
爽快感やカタルシスがあるけどそれは遊園地のアトラクションみたいなもので、僕はそれを作りたいとは思わない。僕が好きな映画というのは、終わった後も自分の中でその映画が育っていくような作品なんです。「あの後、あの人はどうなったんだろう」とか。それから見る前と後で見た人の気持ちが変わったり、見終わった後に一緒に見た友だちや恋人と感想を話すと意見が違ったりする。そういうのがやっぱり僕の思う「いい映画」です。映画を見て嫌な気持ちや重い気持ちになりたくないという若い人も多いと思うんですけど、やっぱり単純に「おもしろかった!」「スカッとした!」だけじゃない映画を作っていきたいし、これからも僕は作っていくと思います。
――『はじまりのみち』では初めて実写映画も手がけられました。アニメ作品でメガホンを取るに当たって原監督は絵コンテを緻密に作り込むことでも知られていますが、実写制作は全く違うものだったと思います。どんな体験だったのでしょうか。
原
最初はやはり戸惑いました。アニメーションは絵コンテで全てのキャラクターの動き、表情を作るんですけれど、実写は役者さんがカメラの前でそれぞれ役になりきってその役なりのしゃべり方や動きを見せてくれる。撮影が始まってみると、自分が思ってもいなかったお芝居が次々と目の前で起きて、それに驚かされたり感動することが多く、そういうのはすごく新鮮でしたね。

――TIFF2017の特集上映で来場者全員に配られる冊子「映画監督 原恵一の世界」のインタビューの中で原監督は「最近のアニメは簡単に泣く作品が多く、観客もすぐに泣く。そんな風潮に『映画をなめるな』という気持ちが強いですね」とおっしゃっています。これは『百日紅~MissHOKUSAI~』に言及したお言葉で、実際『百日紅』では誰も涙を流しません。一方、『はじまりのみち』では加瀬亮さん演じる木下惠介が涙を流すシーンが数回出てきます。涙に対する原監督の思いを踏まえて見ると、これは原監督が計算していたものなのか、加瀬さんが現場の演技の中で出されたものを採用したのか、どちらだったのかと気になったのですが。
原
『はじまりのみち』の泣くシーンに関しては脚本で「ここで涙を流す」というト書きを入れました。それを加瀬さんや田中裕子さんがその通り、涙を流してくれたんです。生身の人間が、脚本にあるそのシーンの人物の気持ちになって、本当に涙を流す姿を、僕は現場で、キャメラの横にいて、1番近くで見ているわけです。そういうシーンに立ち合うというのはすごく緊張もするし、目の前で「ここだ!」というところで加瀬さんが本当に涙を流してくれたりするともう「やったぁ!来たぁ!」という興奮があるんですよね。アニメの涙とはやっぱり重さが違うというか、アニメの涙はいかようにも好きなタイミングでいくらでも流せるので、そういう興奮を経験したことがなかった。
その後の『百日紅』では、僕が作った作品の中でもたぶん初めてだと思うんだけど、誰も涙を流さないということにしたんです。それは杉浦日向子さんの原作に「江戸時代、死は今よりもっと身近だった」ということ、「江戸時代の感情表現は表に出さないことが”粋”である」ということが描かれていると感じたから。だからあえて涙は見せなかったんです。

――”粋”とは少し違いますが、お栄がお猶(なお)を背負って街中を歩いている時、正面から鉄蔵(葛飾北斎)が通りかかる。あの時のセリフがないところでの、しかも引いた画での。
原
すれ違い。
――はい。何とも言えない感情の膨らみが画面からあふれ出てくるようでした。ああいったところは実写ではコントロールが難しいかもなと思ったシーン(※)でもありました。
(※ お猶は重い病を患っているが、父である鉄蔵は滅多に見舞いをしないという関係の中での一幕)
原
いやいや、そこは僕のオリジナルのシーンですけど、ああいう演出を木下監督の映画からすごく学んでるんです。木下監督って引きの画で感情を伝えることがとてもうまい人なんですよね。僕はそういう作品をたくさん見てきて、これまでも、たぶんこれから作る作品でも、一生お手本になっていくと思っているんです。もちろんやろうと思えばキャラクターのアップと切り返しで感情を見せることもできますし、それが必要な時もあります。でもここのシーンの様に、いい意味でそれを裏切る演出ができると、そのシーンがすごく豊かになると僕は思っています。