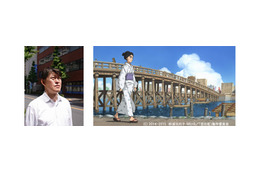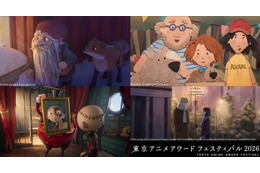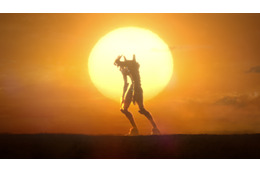原
3DCGのアニメーションに僕はそんなに違和感を抱いていないですし、手描きよりも3DCGで作った方がいいという題材があれば全く抵抗は感じないですね。実写も同じで、その方がいいと思う作品があればやっぱり実写で撮りたいと思っています。
――おお、そうなんですね。
原
アニメーター出身ではないというところが大きいと思うんですけれど、手描きへのノスタルジーはたぶんアニメーター出身の監督ほどないとは思うんです……が。――が、です。日本のアニメーターの手描きの技術レベルはやっぱりものすごく高いんですよ。だからそういう人たちが参加してくれると自分の作品がより深くなるということも分かっているんです。ただ、残念なことに、次の人たちがなかなか育ってこないんです。昔は何でもかんでも手で描くしかなかった。戦車だろうが波だろうが、炎だろうが馬だろうが。でも今はCGを当たり前のように使って、キャラクターしか描けない、という人も増えてきているんですね。3Dで戦車をやるのは正確に描けますからそれはそれでいい。でも馬が出てきて「描いたことないから描けません」というのはね(苦笑)。何でも手描きで描けちゃう人たちもやっぱりいるので。
――手描きの見どころといえば、原監督の作品における背景動画のシーンがあります。『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』はじめ、『百日紅』でも大きな見どころとなっていました。
原
今のアニメの作り方だと、一度3Dで作画用のガイドを作ってからそれに添って手描きの作業をする、となるはずなんですけれど、あそこは絶対、何から何まで手描きの背景動画がいいと思ったんですよね。昔のアニメーションではここぞ!という場面で背景動画を使っていて、『百日紅』はあまり派手な作画の作品ではないですけれど、あのシーンではなぜか一気に雰囲気を変えたくなった。描ける人が誰もいなかったら3Dを導入する選択もありましたけれど、やってくれる人がいた。「ここは手描きの背景動画で、長回しなんだ」と言ったら「やります」と。それでお願いしたんです。

――アニメーションの凄みが溢れたカットでした。実写映画『はじまりのみち』を経て改めてアニメーション映画を手がけるということで、『百日紅』はそれまでの作り方と変わりましたか?
原
うん、変わりました。『はじまりのみち』が終わってからの『百日紅』の絵コンテ作業が苦痛でしょうがなかったです(笑)。『はじまりのみち』ではカット割りなどをリアルタイムに現場のカメラマンの人がやってくれました。僕が「カット!OK」と言ったらどんどん撮影が進んで、ピースができあがっていくんです。こんなにどんどん進んで大丈夫なのだろうかと心配したんですけど、ラッシュで見たら見事に映画になってるんですよ(笑)。その驚きがあったので、「絵コンテなんか描かなくても、ちゃんとした映画は作れるんだな」と思ってしまって。その後の『百日紅』で一コマ一コマ描くのが本当に苦痛でした(笑)。
――あはは(笑)。それでも『百日紅』では緻密な絵コンテに戻られています。
原
うん。でも変化はありましたね。『はじまりのみち』はすごくいいカメラマンさんが付いてくれた。その人の作る画が『百日紅』にもすごく活かされていると僕は思ってるんです。
――ありがとうございます。今までのフィルモグラフィーから続くその先ということで、ざっくりとうかがってしまいますけれど、今後チャレンジしたいことや野望などはあるのでしょうか。
原
僕ももう58才なんですよね。シリーズものではないアニメーション映画の場合、制作スタートから完成までだいたい3年くらいかかることを考えると、自分はあと何本作れるかなと思うようになったんです。それで、今まではあまり積極的に企画を出したりしてこなかったんですけれど、今はすごく、やりたいことや作りたい作品を実写も含めて具体的に提案するようになりました。
――おお、それでは企画が何本か動いているわけですか。
原
ええ。今は新作の絵コンテ作業と作画作業に入っていますけど、終わったらすぐに次の作品に入りたいと思ってます。で、またさらにその次も、と。

――これからはあまり待つことなく原監督の作品が見られるわけですね。
原
うん。もちろん僕だけが思ってできることではないしパートナーがいないと成立しませんが、そうしていきたいです。実写映画も選択肢に入っているので、なるべく間を開けず、時には同時並行しながら作品を作り続けていきたいと思っています。行けるところまでね!
――心強いお言葉です! それでは最後に「アニメ!アニメ!」読者にメッセージをお願いします。
原
自分でも今回(TIFF2017)のラインナップを振り返って改めて、本当にいろんな傾向の、いろんなジャンルの作品を作ってきたなと思います。ここからまたあと30年、作品を作り続けて、もっともっと「よくこんな、いろんな作品を作ったね」と思われるような監督になりたいですね。
――ありがとうございました!