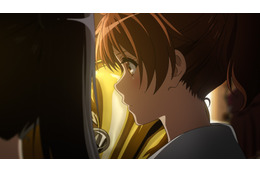高瀬司(Merca)のアニメ時評宣言 第8回 ポストメディウム的状況のアニメーション美学をめぐって 「劇場版 響け!ユーフォニアム」
高瀬司の月一連載です。様々なアニメを取り上げて、バッサバッサ論評します。今回は『劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部でようこそ~』について。
連載
-

「攻殻機動隊」草薙素子、単行本第1巻の表紙でフィギュア化!立てかけて飾れる特別仕様
-

アトラクションのアニメ―『ガールズ&パンツァー』と『KING OF PRISM』/高瀬司(Merca)のアニメ時評宣言 第7回
-

「天穂のサクナヒメ~ヒヌカ巡霊譚~」でもっと米作り! 原作ファンもアニメファンにもたまらない新作ゲームをレポート
ここで急いでつけ加えておかなければならないが、基本的な前提としてわれわれは、デジタル化/ネットワーク化以降に対応する(映像=動画)批評の言葉の構築が急務だと主張しはしても、文化がポストメディウム的状況へと収斂すると断定するほど楽観的な見立てを取ってはいない。(『アニメルカ vol.4』においてポストメディウム的状況におけるフォーマリズムの役割を再検討したように)現に映画批評の場においては、「〈映画〉の現在」のあり方をめぐる模索も継続している。
たとえば映画研究者・批評家の三浦哲哉は『映画とは何か――フランス映画思想史』(筑摩書房、2014年)で、「一方向的に「ポストメディウム状況」が徹底されるという単純な事態があるのではないこともまた確認しておかなければならない。映画がほかの動画と並列化し、ある意味では融合する局面が生まれるのと同時に、その反作用として、映画が映画の固有性を追求し純化するというもう一方の局面がすでに生まれている」(206-207頁)と、「映像=動画」と〈映画〉の二極化の流れがあるとの見立てを示しているし、また(先に注でも触れた)批評家の石岡良治は『ユリイカ』での渡邉との対談で「昨今では映画がマスターメディアから退場したと言われていますが、私のイメージでは相変わらずある種のマスターメディアとして機能しているぞという気がしています。動画の時代になったからこそ、スクリーンで上映されるという条件が重要になっていて、「本篇は映画」という位置付けが明確になっている印象をもちます」(石岡良治×渡邉大輔「「ポスト〇五年=YouTube」の映画をめぐって」『ユリイカ 特集:『スターウォーズ』と映画の未来』2016年1月号、青土社、2015年、63頁)とメディアミックス時代において逆照射される中心性を語ってもいた。
そしてこの動向は、現代の商業アニメをめぐっても見受けられるように思う。
以前も「映像」と「(絵の)映画」という対で語ったが、その一例が、ポストメディウム的状況と共鳴する『響け!ユーフォニアム』に対する、東映動画的な漫画映画の伝統に連なる〈アニメ〉、細田守監督の『バケモノの子』(2015年)である。
ポストメディウム的状況のアニメを考えるとき、その対比は何を照らし出すのか。
補足しつつ概略をたどれば、この両極間の差異は、背景美術に対するアプローチのなかに象徴的に見て取れる。
まず事実確認だが、背景美術もペンタブレットによるデジタル作画が主流となって久しいなか、制作部を解散したスタジオジブリ出身の美術スタッフが手がける『バケモノの子』の背景美術は、すべてポスターカラー=アナログで描かれている。
そのうえで(このわかりやすい対比以上に)何より、『バケモノの子』が――そのバケモノの世界・渋天街は、3Dモデリングソフト・SketchUpで事前に、画面の質感まで含めレイアウトが作りこまれた(渋谷の街はロケハン写真をイメージに合わせ色調補正した)のち、美術スタッフによってその細部まで再現されている(がゆえに描かれたままに近い状態の美術が画面に乗るような)――事前の緻密な設計によって構築された作品【注13】であった他方、『響け!ユーフォニアム』はコンポジットの段階で事前の想定以上の処理が加味される(がゆえに――あくまで極論だが――美術やキャラクターはコンポジット・ワークの素材・フッテージとなるような)ポストプロダクション的作品と見なせる、という対比が決定的である【注14】(もちろんここには、劇場アニメとTVシリーズという条件的な差異はあるだろうが、『バケモノの子』もパッケージの発売により場所を問わず鑑賞可能となり、また『響け!ユーフォニアム』が総集編とはいえ『劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部でようこそ~』(2016年)【注15】としてスクリーンで上映されている現在は、この二極化の先を考えはじめるよい契機でもあるはずだ)。
手描き2Dアニメにおける、東映動画・ジブリを継承する〈アニメ〉【注16】と、デジタル化の先端であるコンポジット・ワークが映すアニメ=映像【注17】。
▼注13:詳細は『ユリイカ 総特集*細田守』2015年9月臨時増刊号(青土社)で筆者が担当した記事の一つである、スタジオジブリ出身の美術監督3人(大森崇+高松洋平+西川洋一)へのインタビュー記事「絵描きたちの創世記」を参照されたい。
▼注14:アニメにおける背景美術の表れ方は、もちろん作品やシーンごとのコンセプトによるとはいえ、傾向としては実写をベースに、ピン送りなども交えつつ、バストショット以上はキャラクターにピントを合わせる(背景はボケる)が、ロングショットはディープフォーカス気味でとらえるというコンポジットが基調となっている。それに対して『響け!ユーフォニアム』は(繰り返すが、ことにファンタジックな世界観ではなく、現代の日常世界が舞台に、ロケハン写真=現実の風景をもとにしたリアリスティックな背景美術を用いた青春ものである点はあらためて注目しておきたい)その極端なシャローフォーカス、そして重ねられるフィルター処理やビジュアル・エフェクトによって、絵として描かれた背景美術を贅沢に飛ばすレンズ的効果が全面展開されている。もちろん、いまやどの作品もていどの差こそあれコンポジットによる処理・効果が全面的に導入されているし、もともとアニメは「(絵の)映画」が志向されていたように、背景美術まで含めショットごとに画角や露出を擬似的に意識したうえで、マルチプレーンカメラなどがあるとはいえ基本的には空気遠近法で奥行きが、またときにはレンズフレアやハレーションまで描きこまれてきた。しかし、それがあくまで「(写真・映像のように)描かれた絵」である点で、『響け!ユーフォニアム』的なレンズ効果とのあいだには断絶を見出だせる。
▼注15:そういえば、『劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部でようこそ~』そのものにはまったく触れていなかったが、編集コンセプトと、それに沿った新規録音により、TVシリーズとは別作品のような驚きを与えてくれる一作として――まさに映像圏的に――再構成されている。そのうえ大流行の兆しを見せている特殊上映もあるという。単なる総集編とは思わないでほしい。
▼注16:しかし同時に、細田もまた、「監視カメラ」というモチーフが印象的な演出家である点は言い添えておく必要があるだろう。つまり『バケモノの子』を渋谷(監視カメラの世界)と渋天街(ジブリの世界)との対比から読み解くこともできるだろうし、またそもそも背景美術をめぐっても、写真への態度という点で、宮﨑(駿)と細田のあいだに切断線を引く(別の二極化を考える)こともできる。
▼注17:あくまで余談だが、劇場公開規模のハイエンドな「ジャパニメーション」から、TVアニメにおけるアラ隠しのための底上げへというサイクルも一巡し、TVアニメの表現を積極的に押し上げるほどの成熟を迎えはじめたコンポジット・ワーク――以前書いた表現を再利用すれば「かつての(あくまで極論だが)撮影台のオペレーターという立場から、1990年代以降のデジタル化の発展を背景に、マシンスペックやソフトウェアの高性能化、デジタルツール/教育の普及およびセクションが担う創造性の急増が推し進めた優秀な若手スタッフの流入、演出陣のコンポジットへの理解度の向上といったポジティブフィードバックの末、2010年代にことさら大きな注目を集めるに至ったデジタルコンポジットというセクション」――は今後、『響け!ユーフォニアム』における過剰で荒々しいインパクトを一つの契機に、(むろんコンポジットによる越権的な画づくりへの関与には賛否両論あるだろうが、TVアニメのスケジュール・制作環境と親和性が高いという現状を前に)少なくとも数クールというオーダーではそのシャローフォーカスやオールドレンズ的表現は顕著な広がりを見せることが予想される。現に『響け!ユーフォニアム』と比べればだいぶマイルドだが、2016年冬クール(1月-3月)を代表する人気TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を』は、その本編のクロースアップを代表に(そしてEDにおける3DCGが用いられたロングショット群でのチルトシフトレンズ的表現も含め)そうした流れを感じさせるシーンに満ちていた。