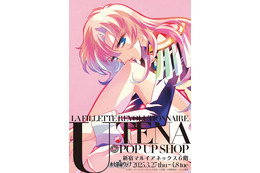■『ウテナ』では現実を超えた世界を作った
――1968年には、背景美術制作会社・小林プロダクションを設立されています。社員の方はお弟子さんとも言えると思いますが、どんなことを教えてこられたのでしょうか。
小林:基本のデッサンができたうえで、表現の自由さを求める姿勢ですね。
自然の中にある現象でも、受け止めるのは個の感性。カメラとは違いますよね。写実的な捉え方はもちろん大事です。
だけども中心は、自分の主観にある。自分の中の自分の思い、自分の癖! しいて言えば個性ですけど、それを活かせと。描き手の個性と作品世界がマッチすることで、ひとつの世界観が生まれる。それが理想ですね。
――カメラではなく、自分の主観なのですね。
小林:見て、感じると言うことは、カメラとはまったく違うんじゃないですかね。目が捉えた視覚的な映像としてのカメラと、心で感じ取ったのは違うでしょう。
やっぱり人間は、驚きと怖さとか、生活感が反映して主観の目線でものを捉え、感じ取っているはずなんです。
――人間の主観を反映した背景と言えば、『少女革命ウテナ』も印象的でした。学園や決闘場など、現実にはあり得ない建物が多く出てきました。幾原邦彦監督とはどのようなディスカッションがありましたか。
小林:幾原さんは、自分の考え方をしっかり伝えてくる方で、この作品は、舞台とか演劇のような世界であり、そのような映像を作りたいと。私にも、現実をひとつ超えて、詩的な作られた世界を求めてくれました。
――実際にはない風景の着想の手がかりとなるモチーフはありましたか。
小林:モチーフも何もないですよ。みんなで、こうかな、ああかなと作っていって、幾原さんからオッケーをもらいながらやっていきました。
私も、幾原さんの言葉を通して私なりにイメージを持ち、「これでどうですか?」「あ、OK」です。だからみんなのアイディアの集合体ですよね。
たとえば、この門は長濱博史さんのデザインなんですよ。とてもいい出来でしたから、それをそっくりいただいて、私の方からは、壊れかけのようなディテールを加えるというやり方もしました。

『少女革命ウテナ』(C)1999 少女革命ウテナ製作委員会
それから、自分なりにこうかな、ああかなと考えたものでは、渦巻き状の階段。あれは私が作っています。
――ウテナと言えば、あの決闘場に向かう場面、あの渦巻き型の階段を!
小林:渦巻き型は幾原さんの要求だけど、どんな渦巻きにするかは任されたわけです。一番てっぺんのほうが天空まできているくらい高いんですね。重力的には持たないような構造でね(笑)。そういうシュールな条件でした。
――心の眼は、物理法則を超えるのですね。では、押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』ではどのような形でお仕事されましたか。
小林:押井さん。あの方は、はっきりおっしゃらないんです。演出上の思い切った設定や意図を出したら、あとは私におまかせです。
たとえば、温泉マークというキャラクターがいるカビだらけになった部屋は、思い切って私にやらせるわけですよ、カビだらけの!(笑)
――夢邪鬼によって永遠の日常が繰り返されるようになった世界で、あたるの担任、温泉マークの住む部屋は時が経ってカビだらけになってしまったというシーンですね。
小林:そう。それで私は調子に乗っちゃってね、絵の具を濡れている石に押しつけたり、吸い取ったり、はがしたりして、カビの表現のマチエルづくりをやりました。
それも押井さんの「カビだらけの部屋」っていう要求でしたから。彼は要求だけはして、あとはおまかせ。できたものに対しては、もう文句は言わなかった。
――おまかせのほうがやりやすいですか?
小林:そうですねぇー……責任を感じますねぇー。押井さんは、シナリオでも絵コンテでも、すべて要求はその中に入ってるんです。
その要求を汲み取るのはこちらの仕事です。相手の意図を探る、“読み合い”の世界なんですね。
■遠くまでクリアに、鮮烈に
――荒々しい激しさや光と陰のドラマを大事にされているということでしたが、ご自身の技法で意識されていることはありますか。
小林:どこかで意識しているもののひとつに、遠近の量でもって強弱を表現している、というのがありますね。たとえばこのロング(遠景)の絵。
――『ビューティフル・ドリーマー』の荒廃した友引町の全景ですね。強弱を量で表すというのは?
小林:遠くもぼかさずに、全部クリアに描く。けれども遠くの奥のほうは、量を少なくするんです。遠くのほうほど線がきれぎれになったり、省いたりとかして細部がだんだんと省略されていく。
そうして奥は量が少なくするんだけれども、手前と同じクリアな部分がちゃんとある。そうすると、遠くのものがカッと強く印象に残るっていう絵になるんです。
――遠くの方ほど面積が少ないから、そこだけスポットライトを浴びているようになるんですね!
小林:そうそう。量の多い少ないに置き換えて、強い弱いを出す。強いものは少ない、しかしそこに確かにある、という
もちろん手前がより強烈にという意識もなくはないですけど、奥の方もクリアで明確でありたい。遠くにはあるけれども荒廃した街並みが広がっているぞと。空と地面との大きな違いを出す、これは意識していますね。
――そこはカメラとは違うのですね。カメラで奥までクリアに撮影しても、奥の印象が強くはならない。遠くまでクリアというのは、人間の心の眼で見たときなんですね。
小林:そうです、そうです。それはオーバーに言えば詩的表現である。あることの強さとでも言いますか、ものがあることの確かさ。あいまいさは好ましくはないですね。遠くがかすみ、ボケるというのは、私は採用していないんです。
――こうした小林さんならではの画風はどのように生まれたかが気になります。
小林:それは自分ではわかりませんけれども。ただ、もやっとしたものじゃないクリアなものが好きですね。
たぶん北海道の寒村で生まれ育ったことも関係があると思います。自然の厳しさというのはごまかしようがない。痛さと似ているんです、寒さって。視覚じゃなくて触覚ですね。
明確な触覚性が自分の中に深く根付いていると思うんです。今は、「触覚性の喪失の時代」だとも思うんです。だからアニメでも、カメラみたいな映像が受け入れられるんです。
→次のページ:ものづくりは闘いだ