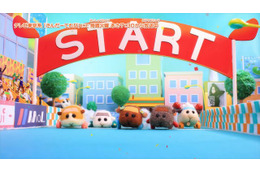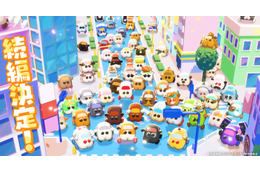辞書をひくと最初に「世界やそこに生きている人間に対するものの見方」という説明が出てくる。例えば「厭世的なものの見方」とか「宗教的世界観」といったものがそれにあたる。
そして次に「その作品が持つ雰囲気や状況設定」(デジタル大辞泉)という意味が出てくる。今回考えたいのは、アニメを語る時にしばしば登場するこちらの「世界観」のほうだ。
しかし、この語釈を見ればわかる通り、こちらの「世界観」には「雰囲気」と「状況設定」という意味合いの違う2つの言葉が含まれており、一筋縄ではいかない。
例えば、アニメにおけるリアリティーラインを現す言い回しとして「2階から落ちた人が骨折するか、痛がるだけで済むか」というものがある。前者であれば、かなり現実に近い表現であり、後者であればいわゆる“漫画っぽい表現”ということになる。
この2つの作品のトーン=雰囲気の違いは、「世界観が違う」という言葉で言い表すことができる。
一方、「状況設定」としての世界観は、物語の舞台や作中で起こることの因果関係などに関わるものだ。物語において「状況設定」は、「物語を推進するキャラクター以外の場所にも作品世界が広がっている」ことを保証する役割がある。
状況設定により、作品世界に「過去」が設定され、「主人公がいない場所」が想定できるようになる。このように状況設定からロジックとして導かれ、生成された背景を、カメラのフレームで切り取ることによって、空想世界に広がりやリアリティが宿ることになる。
『桃太郎』という民話を考えてみよう。
ここで「桃太郎が桃から生まれたこと」や「動物たちとコミュニケーションがとれること」というのは、あくまで民話の中の「トーン」として描かれていることだ。トーン優先で決まっているのが、メルヘン(童話・民話等)の世界といえる。
『桃太郎』の「トーン」による世界観を、「状況設定」から生まれるロジックで考えようとすると、「桃の中から子供が生まれるということはよくあることなのか。あるいは偶然・運命なのか」「桃太郎のお供のイヌ・サル・キジは特別な存在なのか。それともあらゆる動物は人間とコミュニケーション可能なのか」というところを詰めていかないと「世界観」として成り立たなくなっていく。
このギャップは「トーン」で成り立つ「メルヘン」と、ロジックで構築される「ハイファンタジー」の違いといってもいいだろう。狭い意味で使う世界観という言葉の中にも、こうしたギャップが潜んでいるのである。
この「トーン」と「ロジック」をキーワードに、『PUI PUI モルカー』と『えんとつ町のプペル』という2つの話題作に見る「世界観」を考えてみたい。
『PUI PUI モルカー』は、フェルトでできた“モルカー”を扱ったストップモーションアニメだ。
モルカーとは、モルモットが“擬車化”されている存在(あるいは車が“擬モルモット化”された存在)のこと。意志を持つモルカーは、人間を乗せ道路を走るが、同時にキャベツを食べ、困ったことがあれば焦ったり驚いたりと豊かな表情を見せる。
一方で作中に登場する人間は、乗車中は写真で表現され、その動きはあえてカクカクしたものになっている。またロングショットで町並みなどを見せるときは、人間は小さな人形で表現されこちらも、大きく動くことはない。
つまりフェルトで柔らかく表情も豊かなモルカーと、ローファイな表現で描かれる人間の組み合わせることで本作のトーン=世界観は出来上がっているのだ。
と、これだけならば、メルヘンタッチの短編アニメとしてスタンダードな印象で終わっただろう。しかし『モルカー』は、そこにプラスαの要素があった。
それは「モルカー」がキャラクター名である固有名詞ではなく、普通名詞だったという点だ。普通名詞ということは、つまり現実の我々の世界における「自動車」の代わりに「モルカー」がいる世界であるという「ロジック」がそこには潜んでいたのだ。
この「モルカー」というタイトルによって、メルヘン的な「トーン」の世界が、「ロジック」的な広がりを手に入れることができた。
視聴者はモルカーたちの可愛らしさを愛でつつ、フレームの外にあるであろう「モルカーのいる世界」を想像して楽しむことが可能になったのだ。
これが、誰かひとりだけが乗っている特別な存在がモルカーであったら、ここまでの広がりはなかっただろう。
こういう「トーン」と「ロジック」の同居はなかなか難しい要素でもある。
『モルカー』の場合は、尺の短さもあって作中で「ロジック」的に世界観を深堀りする方向にいかないからこそ、「トーン」の魅力と「ロジック」のおもしろさが、やんわりと合一することができたのだろう。
『映画 えんとつ町のプペル』は、煙突から出る煙で空を見ることができない街を舞台に、煙突掃除の少年ルビッチと、ガラクタから生まれたゴミ人間のプペルの交流を描いた作品だ。
本作は、ある程度の文明レベルでありながら、異端審問官の統制により、町の住人は煙の向こうに何もないと信じている、というスタート地点は、「ハイファンタジー」というよりは「メルヘン」と解釈したほうがすっきりする語り口で始まる。ゴミ人間のプペルが生まれるプロセスも、やはり「メルヘン」の領域と解釈するのが素直な表現となっている。
(原作は夜空をかける配達屋さんが、煙をすってせきこんで心臓を落としたことがきっかけでプペルが生まれるという、よりメルヘンな味付けだが、映画はそれとは異なる誕生のしかたとなっている)。
この「トーン」でできた世界観に対し、中盤で「ロジック」が接ぎ木される。
「えんとつ町はなぜ煙で町を覆っているのか」「どうして“外の世界”はなぜないことにされているのか」ということが、「隠蔽された歴史」として説明されるのである。
先述のように「ロジック」によって作り込まれた世界観は、「作品の背景」を支える時に、世界の広がりやリアリティが発生するところにポイントがある。
その「ロジック」を真ん中に据えてしまうと、それは「作者が“神の手”で用意した説明」の範囲に留まり、世界というものが広がりを得ることなく矮小化されてしまう。
このような「トーン」的な発想から生まれた世界観を「ロジック」で落とし込もうする発想は、アニメ映画『あした世界が終わるとしても』や『二ノ国』でも苦労が滲んでいたポイントだ。
本筋である親子のドラマと友情のドラマの不思議な混線を除いても、『えんとつ町のプペル』はそのような「トーン」と「ロジック」の塩梅に苦労が見られる作品だった。
では「トーン」と「ロジック」は相容れないのだろうか。
これは尺の長さ(観客は長尺の作品ほど「ロジック」に寄って作品をとらえていく傾向にある)と、それに対応する語り口(どういう順番で観客に情報を開示していくか)の工夫次第で、いかようにもなるのではないかと思う。
例えば映画『クレヨンしんちゃん』などは、しんのすけというキャラクターの力を借りつつ、「トーン」的な華やかさと、「ロジック」によって作品世界が成立しているおもしろさがちゃんと両立している作品が多い。
その作品がいかに「世界観」を獲得しているか、という視点でアニメを見ると、また別の側面が見えてくるはずだ。
[藤津 亮太(ふじつ・りょうた)]
1968年生まれ。静岡県出身。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』、『チャンネルはいつもアニメ ゼロ年代アニメ時評』、『声優語 ~アニメに命を吹き込むプロフェッショナル~ 』、『プロフェッショナル13人が語る わたしの声優道』がある。最新著書は『ぼくらがアニメを見る理由 2010年代アニメ時評』。各種カルチャーセンターでアニメの講座を担当するほか、毎月第一金曜に「アニメの門チャンネル」(http://ch.nicovideo.jp/animenomon)で生配信を行っている。
1968年生まれ。静岡県出身。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』、『チャンネルはいつもアニメ ゼロ年代アニメ時評』、『声優語 ~アニメに命を吹き込むプロフェッショナル~ 』、『プロフェッショナル13人が語る わたしの声優道』がある。最新著書は『ぼくらがアニメを見る理由 2010年代アニメ時評』。各種カルチャーセンターでアニメの講座を担当するほか、毎月第一金曜に「アニメの門チャンネル」(http://ch.nicovideo.jp/animenomon)で生配信を行っている。