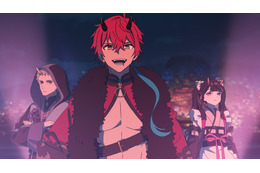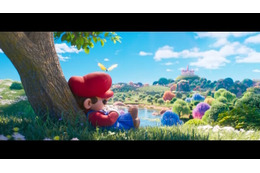『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は技の映画であり、アイデアの映画である。ただしかし“技”や“アイデア”だけを寄せ集めても、子供の作る砂の山のように裾野からさらさらと崩れてしまい、映画のおもしろさは弱まってしまう。技やアイデアを凝集させるためにも、ストーリーという骨組みが必要なのだが、本作の特徴は、その骨組みが骨組みではなく「枠組み」といったほうが正確なほど、ミニマムなものに留まっている点だ。「ミニマムな枠組み」と「たっぷりの技とアイデア」で本作は出来上がっている。
映画は歴史的経緯から概ね90分から120分ほどの長さで、ひとつの物語を語ることが多い。映画の脚本術を説く書籍も、だいたいこの程度の尺長を想定して書かれたものが多い。この長さでひとつの物語を描こうとすると、主人公の葛藤と変化にフォーカスすることになる。様々なストーリーテリングを解いた書籍に書かれているように、多くの主人公はなにか「欠如」を抱えている状態から始まり、特別な場所へ「行って還る」過程を経て、欠如したなにかが補完されるという道筋をたどる。これは普遍的な物語の形で、さまざまな作品に骨組みとして採用されている。観客は、主人公が欠如を補完するものを求める過程で葛藤する過程でドキドキハラハラし、そしてそれを獲得する瞬間にカタルシスを得る。この“欠如”は、具体的な欠如に限ったことではなく、ドラマを生み出す種といってもいい(もちろん探偵もののように、主人公が狂言回しで、ドラマは外部のキャラクターが持つ場合もあるが、それはここでは一旦置いておく)。
問題は、ある原作を取り上げて映画を作ろうとした時、原作に2時間の映画を支えるだけのドラマの種が明確な形で存在していない場合があることだ。その場合、映画化の過程でドラマの種を加える必要が出てくる。あるいは、主人公はドラマの種を持っていても、原作が完結していないため、このドラマの種を(原作の完結に先んじて)作品の骨格にするわけにいかない場合もある。いずれにせよ映画の骨組みを構成するためには、「なにか」を加えざるを得ない場合は往々にしてある。
例えば『シン・仮面ライダー』では、作品のキーアイテムである「仮面」を物語の中心に据えた。そして「仮面」をかぶると非人間的な暴力を振るうことが可能になった主人公・本郷猛の葛藤を中心に据えた。そして「非人間性の象徴である仮面」は本郷の葛藤と戦いを通じて、「(人々の)人間性を守る象徴としての仮面」へと上書きされるのである。ここではTVシリーズや漫画版にある断片的なモチーフをパーツにしつつ、映画用のドラマの種と主題を編み上げている。
逆に苦労がうかがえる例としてよく挙げるのが『科学忍者隊ガッチャマン』を原作とした実写映画『ガッチャマン』だ。原作となったTVシリーズは、ドラマチックな各エピソードはあれど、1970年代初頭のTVシリーズだから、シリーズ全体を貫く主題があるわけではない。そこでドラマの種を考案する必要があり、実写映画は、健とジョー、そして敵ギャラクターの襲撃により行方不明となった2人の幼なじみ・ナオミの関係性を、骨組みとして採用した。ナオミの不在が「欠如」というわけである。
しかし、ナオミは原作に登場しない人物なので、彼女をめぐるドラマを深めるということで、どうしてもTVシリーズからの距離が生まれてしまう。とはいえ『ガッチャマン』の場合、TVシリーズの中の何を骨組みの根拠としてピックアップするかは、なかなか難しい問題でもある。(個人的には健と因縁がある。レッドインパルス隊隊長をうまくピックアップしたほうがよかったのではないかと思っている)。
こうした例を念頭において『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を見ると、いろいろ見えてくるものがある。
冒頭はニューヨークのブルックリンで配管工として働いているマリオとルイージの姿から始まる。しかし彼らは誰にも認めてもらえておらず、特に父親に認めてもらっていないことはマリオを悲しませている。
本作はこのように「主人公が抱える欠如」をドラマの種としてはっきり投入するところから物語を始める。ポイントは本作がそうやって始まるにも関わらず、父親を代表とする周囲の人間が自分を認めてくれないこと――をめぐる物語という方向に進まないことである。このドラマの種を深めていくと、(原作ゲームには登場しない)父親とマリオの物語になってしまう。それでは原作ゲームから遠くなる道だ。ここで示されるドラマの種は、本作をお話として始め、お話として終わらせるための「枠組み」に過ぎない。
だから異世界に飛ばされた時点で、マリオの動機は「囚われのルイージを救う」へと“すり替える”のである。ルイージである理由も明白で、原作ゲームのようにピーチ姫を救う物語にしようとすると、ピーチ姫との関係性(恋愛であろうがなかろうが)を描かなくてはならなくなる。それを描写するにはそこそこの時間が必要だし、そこを見たい人がどれぐらいいるかも難しい問題だ。となれば最初から人間関係のできているルイージをマクガフィンとして設定するのが効率がいい。
こうして最短距離でセッティング=枠組みを構築できたらあとは、魅力的なプロダクションデザインを構築し、そこにアクションとユーモアをいかに詰め込むかにアイデアを凝らせばいい。ここのアクションとユーモアの密度が本作の満足度を左右することになるので、本作のクリエイティブのキモである。アイデアこそが重要で、マリオの心理的な変化は中心にはならない。
とはいえ序盤に仕込んだ「自分を認知してもらう」という枠組みも忘れてはいけない。そこで物語を終わらせるために、ラストは現実のブルックリンに舞台を移して締めくくられるが、既に確認した通り、マリオが町の人々から承認されるかどうかは「枠組み」でしかない。マリオの人物像が、初登場時から大きく変化していない以上、クライマックスのアクションはマリオの何かを象徴するわけではなく、楽しいアクションそのものとして描かれる。結果として、父からの承認に至る段取りも描写も通り一遍のものになる。
本作の高い評価は、こうした「シンプルな枠組みの中に、密度高くサービスを詰め込んだこと」に由来している。
つまり本作は、ギリギリのところでドラマを回避する(枠組みに留めて深掘りしない)ことで、「マリオ」というアイコンを扱った「映画」として成立しているのである。これは生身の肉体が画面にうつる実写映画では不可能といっていいだろう。
「枠組み」があるだけという点で考えると本作は、近年増えている映画館で上映される「アニメ・ゲーム由来のアイドルキャラクターのフィルムコンサート」と距離が近いことも見えてくる。ドラマ的な枠組みは最低限に抑えられ、その枠組の中で、キャラクターの魅力を最大限に引き出すようアイデアが凝らされる映画。そこではキャラクターは変化することなく、「みんなの愛するキャラクターである」ことを永遠に提供し続ける存在として登場する。この共通点を意識すると、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の本質は、マリオというキャラクターの「ライブ」であったとも解釈できるし、映画館が「疑似ライブ会場」あるいは、4DXなどの普及にみられるように「身近なテーマパーク」として発見されている大きな流れの中に本作を位置づけることも可能になる。
最後にもうちょっと大きな視点で考えてみよう。少し前に、あるトークイベントで、メタバースの可能性を巡る話題からMMORPGの例が挙げられたことがあった。かい摘んで紹介をすると、ゲーム参加者同士のコミュニティができるまでは様々なゲーム内でのイベントが大きな役割を果たすが、ある程度人間関係ができると、イベントの優先順位が下がり、参加者同士のコミュニケーションの優先度が上がる、という傾向があるということだった。
おそらく長い間愛されているキャラクター・世界観も似たようなところがあるのではないだろうか。長い間愛されれば愛されるほどファンはイベント=ドラマを必要としなくなっていく。キャラクターや世界観は一種のインフラ化・環境化していくのではないだろうか。逆にいうと「いつもその状態でなくてはならないもの」として、「おかわり」を待ち続けるファンから安定供給を期待されるものになっていく(でも同じものばかりだと「飽きた」といいだすのもファンの常であったりする)。キャラクターや作品世界を扱う資本主義の洗練の結果として、ドラマはギミック化し、キャラクターや作品世界は“福祉”のように求められるようになるのだろう。