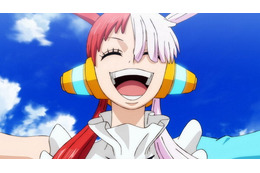■ルフィとウタは“対照的”に存在する
こうして考えると、異色作ともいわれる『RED』も、基本の構図の作り方はこれまでの「FILM期」の作品――特に『Z』と『GOLD』――と大きくは異なっていない。例えば、『Z』の敵役ゼットも、『GOLD』の敵役テゾーロも、それぞれの人生の中から己の行動を決定し、その結果、ルフィたちと戦うことになった。そして2人とも非常に強かった。『RED』のウタも、自らの人生を踏まえて決意し、行動を定め、結果、ルフィたちと対立することになった。
では『RED』が「FILM期」の定石をなぞっているだけかといえば、当然ながらそんなことはない。『STRONG WORLD』と『GOLD』は、上下方向の動きによって支えられた作品だった。『STRONG WORLD』の敵役・金獅子のシキは重力コントロールができるフワフワの実の能力者であり、空飛ぶ島メルヴィユから「東の海」などを支配しようと目論んでいた。また特に『GOLD』は、巨大黄金船「グラン・テゾーロ」内での上下動が、そのままテゾーロの支配構造を示す映画になっていた。
一方『Z』は上下移動の映画ではなく、クライマックスのルフィとゼットの殴り合いに象徴されるように、同一平面上で様々にベクトルがぶつかり合う作品だった。これに対し『RED』は「上下動」でも「同一平面」のどちらでもない。『RED』においてむしろ重要なのは「同一平面上に見えながら同一平面上ではない」という点だ。だからベクトルがぶつかり合いそうでなかなかぶつからない。なぜなら本作は「重ね合わされた2つのレイヤー」による映画だからだ。
この2つのレイヤーはまず映像としては、ウタがウタウタの実の能力によって、ルフィたちや観客を虜にした「夢」の世界と、「現実」の世界という2つの形として劇中で描かれる。そしてその延2つのレイヤーは、あくまでも「現実」に立脚するルフィと、「夢」に立っているウタのすれ違いという形でドラマに投影されていく。
もともとルフィとウタは対照的なキャラクターだ。シャンクスの精神的息子のルフィと、シャンクスに娘として育てられたウタだが、ルフィは「海賊王」を目指し、ウタは「海賊嫌い」。ルフィがシャンクスを慕っているのに対し、ウタは自分がシャンクスに捨てられたと信じている。
また、ルフィには仲間がいるが、ウタには仲間はいない。そのかわりルフィにはいない、メディア(映像電伝虫)の向こうに大勢のファンがいる。ルフィが「手で触れられるリアルな世界」に生きているのに対し、ウタは「夢」や「メディアの向こうにいる他人」を自分の世界としているのである。
よく似ている場所に立っているのに、それぞれのあり方は重なり合わない。ここに2つのレイヤーが重なりつつも、決して同一化しない様子を見ることができる。
そういうふうに考えると、「幼い頃からの勝負の結果をルフィとウタが正反対に覚えている」というたわいないエピソードも、2人の生きるレイヤーが違っていることの表現のように見えてくる。また、ルフィがクライマックスのバトルで、ウタそのものを殴らなかった、(心情的な理由ではなく)映画的な意味合いとして解釈できるようになる。お互いが生きるレイヤーが異なっているのであれば、ゼットの時のように、互いの生き方のベクトルをぶつけ合うように殴り合うことはできない。
エレジア島で孤独に育ったウタには「現実」がわからないのだ。だから「夢」の中に入ってしまえば幸せだというふうに考えてしまった。しかもそれは彼女が背負った「現実」の重さや辛さを、そのままメディアの向こうにいるファンの「不幸」に投影した結果でもあった。
ウタの運命が決してしまった今、「もしも」を考えることにはなんの意味もない。でも、島で孤独に勉強しているウタの姿を思い出すと、この時期になんとか集団生活をする機会が得られなかったのだろうか、と思ってしまう。もしそうであれば「現実」の意味も、きっと学べたはずだし、人生において「現実」と「夢」のレイヤーが、相互補完的に働いていることが理解できたのではないか。だが、彼女にはそういう人生は訪れなかった。
『RED』で観客は、そんなウタの人生に立ち会うことになる。劇中に登場する7つの楽曲は、“ほぼミュージカル”といってもいいほど、彼女の人生の決断と逡巡を直接的に語っている。そして映画は彼女を「不幸であった」と涙を絞るように語ることもなく、かといって「自分勝手に世界を勘違いした少女の末路」と皮肉な視線で描くこともしない。ただ「こんな女の子がいました。彼女の歌は、彼女がいなくなっても多くの人に愛されています」とまるでおとぎ話のように静かに締めくくるのだ。
ウタは不幸だったのだろうか。クライマックスのバトルから、物語の終りに至るまでの展開を見ると、この映画は「幸福かどうか」で人生を計っていないことがわかる。ここで尊重されているのは「自分の人生は自分で選ぶもの」ということである。ウタはすべてを知って、自分の計画を発動し、それが綻び、失敗とわかった時には、薬を飲んで自分が助かるよりも、夢から人々を開放することを選んだ。それはすべて自分の決断で、そこには一点の曇りもない。「不幸かどうかは見る人が判断すればよいこと」だが、彼女が彼女の人生を生きた、ということは紛れもない事実として描き出される。そしてそれはそれとして、彼女の歌を楽しむ人たちに彼女の人生はまったく関係のないものだ。
この徹底した「その人の人生はその人(だけ)のものである」という思想。そこに向かって本作が進んだ以上、最後にルフィのお馴染み「俺は海賊王になる」という台詞が置かれた意味もまた見えてくる。
おそらく当初は、“異色作”といわれるであろう『RED』の終幕に際し、「これで本作は終わり、いつもの『ONE PIECE』の世界に戻りますよ」という宣言としてこの台詞が置かれていたのではないだろうか。しかし「その人の人生はその人(だけ)のものである」という思想を重ねてみると、ウタはウタで自分の人生を生き抜き、それと同じようにルフィもまた自分の人生――「海賊王になる」――を生きようとしているのだ、という意味合いが生まれてくる。
とても近いところにありながら、重なることはなかったウタとルフィの人生。重なることのなかった相手の人生など、背負うことはできない。できるのはせいぜいが「お前はそっちの道を選んだんだな。俺はこっちの道をゆくよ」と、自分の道を飽かず歩み続けていくことしかできないのだ。
そしてこの「自分が選んだ道しか歩けない」という主題は、2000年の第1作『ONE PIECE』で、海賊になることを誘われながらおでん屋になった岩蔵じいさんの生き様をも思い出させるのだった。