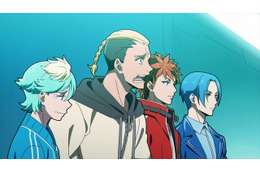2021年3月8日(月)、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開された。これでやっと「エヴァ」は筆者の中で「思い出」のフォルダに仕舞われることとなった。
1997年の夏、徹夜で並んだ劇場で「気持ち悪い」と言われっぱなしのまま館内が明るくなったあの時から、ずっと「エヴァ」は終わっていなかった。納得いかないけれど、むしろ納得できないところが「エヴァ」らしくていいと、あの時は自分に言い聞かせていた。
しかし、本来は別の可能性もあったはずなのだ。キレイに完結する「エヴァ」という可能性が。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は想像以上に見事に完結していた。1995年放送のTVシリーズでやり残したこと、さらに97年の劇場版で描ききれなかったこと、それら全てにしっかり決着をつけていた。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」公開日の写真。座席状況(著者撮影)
鑑賞する直前まで、「エヴァ」はある意味、完結しないことに美学があるのだ、という97年の気分は抜けていなかった。だからこそ、こんなにもしっかりと「エヴァ」が完結したことに驚きを隠せなかった。
驚きはそれだけではなかった。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』には、これまで庵野秀明監督が描いてこなかった(あるいは描けなかった)ものを描いていたように思う。本作で庵野監督は、名もなき人々の小さな営み、ささやかな生活を守ることを称賛した。
かつて宮崎駿監督は、97年時点の庵野秀明監督に対して、群衆を描けないと批判したことがある。一般に旧劇と呼ばれる『新世紀エヴァンゲリオン』の戦闘シーンには確かに群衆はほとんど登場せず、物語も碇シンジの半径数メートルの人間模様ばかりが描かれる。
アニメで群衆を描くのは大変な作業だ。しかし、宮崎監督は群衆一人ひとりにも魂があるのだと言わんばかりに、『風立ちぬ』で大変な手間のかかる群衆シーンを描いていた。そういう姿勢はかつての庵野監督にはなかったのではないかと思う。
しかし、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』では、群衆がはっきりと意識されるようになった。『:序』のヤシマ作戦で名もなきエンジニアたちが必死で設備を組み立てていたのを観た時にも大きな変化を感じたが、本作ではより踏み込んで市井の人々の生活を描写し、それをかけがえのないものとして描いている。子どもを産み育てること、食物を作ること、日々働くこと、挨拶をすること……。そんな当たり前の日常をきちんと過ごすことが一番大切なことだという。
その人々の営みは、戦後日本の復興のようにも見えるし、東日本大震災から復興しようとしている東北の人々にも重なって見える。『シン・ゴジラ』で戦後日本と3.11後の日本を描いた庵野監督だからこそ、そのような要素が入ってきたのかもしれない。
そして、最後にはきっちりと碇シンジという少年の心の旅路に、様々な要素を抱えながら、これしかないという決着の付け方をしてくれた。父子の対立の物語はありふれているかもしれない。しかし、そんな当たり前のことを正面きって描くことは、「エヴァ」を終わらせるために絶対に必要な「通過儀礼」だった。そして、通過儀礼の後に待っていたのは当然のように成長だった。
「エヴァンゲリオン」が思い出になる。それは取りも直さず「成長」するということだ。人がいつか成長するなんて当たり前のことだが、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はその当たり前に改めて真摯に向き合っていた。そんな当たり前のことに向き合いきれなかった筆者のような人間には、その当たり前が眩しい。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」500ピースジグソーパズル(著者撮影)
今、「思い出」として振り返ってみると、「エヴァ」について考え続けた26年も悪くなかった気がする。「エヴァンゲリオン」という現象は、間違いなく良い思い出だと今は断言できる。
「思い出」になるというのは、過去のものになるということだが、過去のものにできるということは、とても幸せなことなのだ。
※本文内画像は、著者・編集部撮影