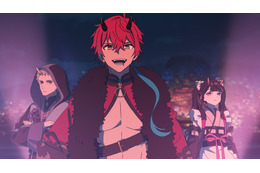今回はこの『アニメと戦争』の「追補」ということで、物量の問題や話題の流れが理由で本書の中に組み込めなかった話題をひとつ取り上げたい。取り上げるのは『今、そこにいる僕』。同作は1999年10月からWOWOWで全13話が放送された作品だ。
平凡な中学生・シュウは、学校の帰り道に不思議な少女、ララ・ルゥと出会う。そこに竜のような奇妙な機械に乗った兵士が現れたかと思うと、シュウは突然見たこともない世界に立っていた。
その世界では、要塞ヘリウッドの独裁者ハムドが、少年兵などを使ってその支配範囲を広げようと戦争を行っていた。
作中ではヘリウッド以外にも“国家”があると言及しているが、そことの戦争はさほど明確に描かれない。むしろ物語で重要な意味を持つのは、小さな村ザリ・バースとの関係だ。
ザリ・バースの中にはハムドを暗殺してしまおうという一味が存在し、一度は暗殺を試みている。そのほかの描写を見ても、ヘリウッドとザリ・バースの関係はヘリウッドの影響圏内で起きている内戦状態と考えたほうがより近い。
本作は当初、戦争をしている異世界に飛ばされた少年の冒険を描く明朗なプロットだったという。
しかしその最初のプロットを書いた後、監督の大地丙太郎はアフリカの少年兵を扱ったドキュメンタリーを見たことで方向性が変わる。
「それで最初のプロットに少し、戦争の悲劇や深刻さを入れようと思ったんです。やっぱり戦争を茶化しちゃいけないんじゃないか、という考えがあったかな」(「今ここにいる対談」より。「『今、そこにいる僕』完全保存版シナリオ+データブック」所収)
こうして企画はぐっと生々しい方向に舵を切ることになる。
「実は、異世界に行く話は、自分が作るのは嫌だったんです。でも、もし異世界モノをやるなら、本当に自分が行ったらどんな気持ちだろう、という生々しい感覚を狙いたかった。今、戦争をやっている国が実際にあるわけで、突然そこに飛ばされたらどんな心境になるだろう…って。
まあ、現実的には逃げて、オシッコ漏らして、ってなっちゃうだろうけど。その辺は、シュウを一途で負けないヒーローっぽい性格にして、物語らしくはしています。でも気持ち的には、リアルに響く感覚にするように心がけたんです。」(同書)
大地監督はギャグやコメディを中心とした仕事が多く、その中にあって本作は「異色作」である。だからこそ積極的に「ジャンル化した(ロボットものを中心とする)戦争アニメ」に対するカウンターを作ろうとしていたことが発言から伝わってくる。
ロボットアニメにおいて少年・少女がパイロットになるのは、そもそもは視聴者の年齢層を意識していたからである。社会的になんの力も持たない子供が、ロボットという力を通じて力を行使できるようになる(社会にコミットできるようになる)。
それは現実の子供たちにとって十分楽しく、感情移入できる要素である。魔法少女の「魔法」や変身ヒーローの「変身」も似たような意味合いを持ったエンターテインメント要素だ。
だが、ロボットアニメの場合はそれが「悪の組織との私闘」から「戦争」へと変質したことにより、10代のパイロットという存在は複雑な色合いを帯びるようになった。
『今、そこにいる僕』は、その部分を直視しようとしたのである。
大地の発言にあるようにシュウという主人公は、物語を停滞させずエンターテインメントとしての枠組みをはずさない狙いもあって、ヒロイックでめげない性格の人間として設定されている。
だが、だからこそシュウの言動は物語の中では慎重に扱われていて、彼の言動はしばしば厳しい現実と噛み合わない「空回り」としても描かれる。
またクライマックスでも、主人公らしくアクションを展開したりはするが、それはあくまで怒りという感情の発露としてだけ描かれて、ヒーロー然として見えないように演出されている。
このようにロボットアニメの主人公像に対してある種の批評性が込められた本作だが、“戦争描写”として一番踏み込んでいるのは、捕虜となった女性キャラクター、サラの性被害を描いた点だろう。
本作は第12話「殺戮の大地」で、ヘリウッドが進軍してザリ・バースを蹂躙するシーンを描いているが、そこでは虐殺とその結果としての死体の山を直接的に見せている。これも踏み込んだ描写ではあるが(おそらくこれが放送できたのは、地上波ではなく衛星放送であるWOWOWだったからではないだろうか)、サラのエピソードの重さはそれ以上のものがある。
サラは第3話「闇の中の宴」で登場する、アメリカ出身の少女だ。
彼女は、ヘリウッドの軍隊が別の世界に逃げたララ・ルゥを探す過程で、人違いの結果この世界に連れてこられてしまったのだ。
人違いとわかった後も彼女は投獄されたままで、シュウと出会うことになった。持ち前の明るさで「生きていたらいいことがある」とサラを励ますシュウ。
ララ・ルゥが持っていたペンダントの場所を吐かせようとシュウが拷問に合う一方で、サラは少年兵たちに連れられてある部屋まで連行される。
部屋の扉が開くと、「死んだ魚のような目」(脚本のト書き)の兵士が、サラを部屋へと引き入れる。
時間が経ち、拷問でボロボロになったシュウが牢獄へと戻される。床に倒れたままのシュウは、サラの服が破れていて、ボタンもとれており、彼女がヘリウッドの兵士に強姦されたことに気付かない。
このシーンは映像でしか語られないが、前半のシュウの励ましが皮肉に響く、とてもシビアな描写だ。
第3話に続いて第6話「砂嵐に消える」冒頭でも、サラが兵士のもとへと送り込まれるシーンが描かれる。
サラが兵士の部屋に入ると、兵士はサラを値踏みするような目で見て、「使えねぇわけじゃねぇなぁ。ちと貧弱だが」と口にする。さらに「これもハムドの命令だからな。せいぜい丈夫なガキを産めよ」と台詞を重ねる。
ここに続く「俺の子なら、丈夫に決まってる」「いい兵隊になる。俺みたいな」という台詞が、この兵士が極めて“普通”の人間であることを感じさせる自然さで演じられており、だからこそサラの存在が逆にまったく尊重されていないことが際立つ。
兵士は、行為が終わったら貴重な水を飲ませてやる、とも言うが、おそらくこの兵士にとってそれは「奴隷にみせる、ちょっとした優しさ」のつもりであろう。
この兵士の会話の「そこでひとりの人間の尊厳が奪われていることに気付かないことが当たり前になっている」という状況は、視聴者に鋭く迫ってくる。
戦争という複雑なものの全てを描くのは難しいが、それでも戦争を題材にするのなら、せめてなにかひとつでも、ほかの作品では触れていないものを作品に取り込み、視聴者に伝えようという執念が感じられる。
一方、サラはこの兵士が上着を脱ごうとした瞬間、机の上にあった、水の入った金属製の重そうな水筒を手にして殴りかかる。2人はもみ合いになり、サラは口を塞がれて殺されそうになる。
だがサラはなんとか抵抗しライフルの銃床で兵士を殴打し、最終的に兵士を殺してしまう。このあたりの兵士を殺すまでの段取りは脚本から映像化される過程でかなり膨らませてあり、生々しさが一層増している。
こうしてサラはヘリウッドをなんとか逃げ出すが、やがて彼女は父親が誰かわからない子供を妊娠していることがわかることになる。
このようにサラが、戦場で性的な奴隷として扱われたということは大きなサブストーリーをなしている。
女性が「戦利品」の一種であり、さらに「自国のために子供を生む道具」として扱われるという部分を正面切って描いたという点は、そのほかの戦争を扱った作品から本作が一線を画す、重要な要素となっている。
最終回、すべてが終わった後、シュウはもとの世界へと戻ってくる。それは別世界へと連れさられる前と同じ夕方。ただし、ララ・ルゥを連れ戻そうとした時、ヘリウッドの兵士たちが破壊した煙突はそのまま壊れたままである。
そこから「戦争のある国」に連れされてシュウが経験したことが、まるで夢のように感じられ、でもそれは決して夢ではない、という二重の情感が生まれる。それはそのまま視聴者にとって「これはアニメである」ということと「でも世界のどこかで起きていることでもある」という二重のメッセージでもある。
第二次世界大戦が歴史的事実から遠くなり、細部が趣味として消費されるようになる――アニメはこの「戦争のサブカルチャー化」という大きな傾向の中に存在している。
だが『今、そこにある僕』は作品を「現在のどこかに起きている戦争」と繋ぐことで、その流れの中に一石を投じようとしたのである。
それは『火垂るの墓』のラストが現代の風景であることの延長線上にある試みでもある。
ひとつ付記すると、現実の少年兵たちはもっと狂信的で(それはつまり純粋ということでもある)、本作のようにわかりやすい子供らしさを残しているというわけではないようだ。
だが『アニメと戦争』の第十章で『この世界の片隅に』の話題に関して引用した通り、「狂信的な人間」というものを、変化していく過程がなく日常の風景としてアニメ(や漫画)で描くと、その人が愚かな人に見えてしまうという現象が起きてしまう。
視聴者と常識の水準が異なりすぎて、視聴者が「この人たちは愚かだからこんな狂信的な振る舞いをするに至ったのだ」と考え、自分と地続きの存在とはとらえなくしまうのだ。
そうすると、視聴者を「そこにいる」状態にすることは難しくなる。普通の視聴者に作中の戦場を実感してもらおうとするなら、現実に即した「(現在の我々から見た)狂信的な人物」が阻害要素になる場合があるのである。
以上のような挑戦と工夫を意識しつつ『今、そこにいる僕』を再見すると、さらなる発見があるのではないだろうか。
以上、『アニメと戦争』の追補である。
[藤津 亮太(ふじつ・りょうた)]
1968年生まれ。静岡県出身。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』、『チャンネルはいつもアニメ ゼロ年代アニメ時評』、『声優語 ~アニメに命を吹き込むプロフェッショナル~ 』、『プロフェッショナル13人が語る わたしの声優道』、『ぼくらがアニメを見る理由 2010年代アニメ時評』などがある。ある。最新著書は『アニメと戦争』。各種カルチャーセンターでアニメの講座を担当するほか、毎月第一金曜に「アニメの門チャンネル」(http://ch.nicovideo.jp/animenomon)で生配信を行っている。
1968年生まれ。静岡県出身。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』、『チャンネルはいつもアニメ ゼロ年代アニメ時評』、『声優語 ~アニメに命を吹き込むプロフェッショナル~ 』、『プロフェッショナル13人が語る わたしの声優道』、『ぼくらがアニメを見る理由 2010年代アニメ時評』などがある。ある。最新著書は『アニメと戦争』。各種カルチャーセンターでアニメの講座を担当するほか、毎月第一金曜に「アニメの門チャンネル」(http://ch.nicovideo.jp/animenomon)で生配信を行っている。