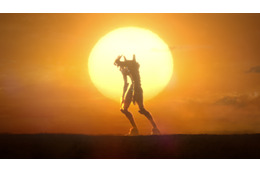「アニメ」の概念とは?その混沌について 藤津亮太のアニメの門V 第16回
アニメ評論家・藤津亮の連載「アニメの門V」。第16回目は「アニメ」とは?という議題について。毎月第1金曜日に更新中。
連載
-

“忍者”キャラといえば? 3位「忍たま乱太郎」乱太郎、2位「NARUTO」うずまきナルト、1位は“初恋キラー”の呼び声高い… <26年版>
-

『マクロスΔ』に見るシリーズ作品の自由度 藤津亮太のアニメの門V 第15回
-

「天穂のサクナヒメ~ヒヌカ巡霊譚~」でもっと米作り! 原作ファンもアニメファンにもたまらない新作ゲームをレポート
こういう場所にくると、いつも考えてしまうことがある。それは「アニメ」とはなんだろう、ということだ。
まず「アニメ」は「アニメーション」の略語として生まれた。さまざまな定義付けが可能であろうアニメーションだが、ここでは「コマ撮りによって動きをクリエイションすることを前提にした芸術形式一般」と定義しておこう。
ところが'77年以降、略語だった「アニメ」の意味が、微妙に変質する。それまで子供向けにテレビまんが、漫画映画といわれていた作品群と一線を引くために、10代以上のファンが好むような作品が“アニメ”と呼ばれるようになった。のだ'77年の劇場版『宇宙戦艦ヤマト』公開をきっかけとして、ポピュラーになった、若者文化としての「アニメ」の誕生である。
やがてアニメという言葉がポピュラーになるにつれて、いわゆるハイターゲット向けの作品でないものも包括して“アニメ”と呼ばれるようになった。ここに“アニメ”という言葉の複雑な色合いがある。「アニメっぽい」と言われる多くの場合、それは「ハイターゲット作品に類する雰囲気」を指していると考えたほうが頷ける。
つまり「アニメーション」の中に「アニメ」があり、しかも「アニメ」の中には「アニメっぽいアニメ」と「アニメっぽくないアニメ」があるというわけだ。
そしてこうなってくると「アニメっぽくないアニメ」の中には、限りなく「アニメーション」に近いものも現れてくる。たとえば『アニメ(ーター)見本市』の中の何本かは、インディペンデントな個人作家の作品と極めて接近してくる。
新千歳国際アニメーション映画祭でも『アニメ(ーター)見本市』は上映ラインナップに入っている。「アニメ」という言葉のとらえどころのなさを前提に、こういう状況を見ると、もはや「越境」というより、「混沌」という言葉のほうがふさわしいようにも思えてくる。
ビジネスの局面であれば、クリエイターの出自や所属する業界、あるいは流通経路というものを背景に「アニメ」であること(あるいは「アニメ」でないこと)を前面に打ち出すことに意味があるかもしれない。でも、「映画祭」という解放区では、そんな必要はない。いちいちそこに線を引かずに、あらゆるものが「混沌」なら「混沌」のままにひとつのテーブルの上に繰り広げて見せるのは「祭」としては自然なありかたとも思える。
ちなみに「アニメ」という言葉を取り巻く混沌は、'00年代に入ってからさらに複雑になっている。それは3DCGの普及による、アニメと実写映画の接近である。
押井守監督は'01年の『アヴァロン』公開時に「すべての映画はアニメになる」というテーゼを唱え始めた。
3DCGなどとの合成カットの増加は、映画が最終的にコンピューター上で完成する時代が到来したということだ。こうなると実写映画において特権的な空間であった「撮影現場」は、「よい素材を手に入れるための重要なプロセス」のひとつになる。そのかわり問われるのは、最終的な映像ビジョンを定め、そのためにはどういう素材が必要なのかを考えられる、アニメの演出家としての発想が武器になる、と。これが「すべての映画はアニメになる」という言葉に秘められた意味だ。
この言葉のストレートな実践として'16年の『シン・ゴジラ』を挙げてもよいだろう。事前にプリビズを制作し、それの完成にめがけて“素材”を集めていった『シン・ゴジラ』のマインドはアニメに極めて近い。
もちろん『シン・ゴジラ』は実写で特撮と分類される。だが、同じアニメーションの枠内にある抽象アニメーションとTVアニメの距離を考えてみると、むしろTVアニメと『シン・ゴジラ』のほうが距離が近いと考えることもできる。
実写がアニメ化しているだけではない。
日本のアニメは、「カメラを向けてあたかも風景を切り取ったように見せる」という自然主義的な方法をもとにリアリティを獲得してきた。'16年を代表する作品ともいえる『聲の形』と『この世界の片隅に』が、アプローチは別々だが、「その空間・瞬間を世界から切り取ってみせる」ということに力を入れて演出していたことも忘れてはいけないだろう。どちらの作品も、キャラクターの存在する現場に観客を立ち会わせようとしたからこそ、そこに力が入れられていたのだ。
そういう意味では、実写がアニメになるだけでなく、アニメもまた実写(より正確にいうと概念としての“カメラ”)をエミュレートして取り込もうとしているのだ。しかもこの自然主義的指向性は、'40年近くかけて、「アニメ」には必須の要素となっている。『聲の形』と『この世界の片隅に』はその歴史の果ての2本なのである。
「アニメ」という言葉が何を指しうるか、というその境界線に生まれる混沌についていろいろと考えてみた。実はアニメの研究で一番望まれているのは、このあたりの概念整理なのかもしれない。
[藤津 亮太(ふじつ・りょうた)]
1968年生まれ。静岡県出身。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』、『チャンネルはいつもアニメ
ゼロ年代アニメ時評』がある。各種カルチャーセンターでアニメの講座を担当するほか、毎月第一金曜に「アニメの門チャンネル」(http://ch.nicovideo.jp/animenomon)で生配信を行っている。